ビュクリュカレ
松村 公仁 アナトリア考古学研究所研究員
第8次ビュクリュカレ遺跡発掘発掘終了報告(2016年)
6月にビュクリュカレ遺跡の発掘が終わるとすぐにカマン・カレホユック遺跡の発掘が始まり、それが終わってヤッスホユック遺跡の発掘が始まる9月になると大学の新学期が始まります。11月には一般調査もあり、外での調査活動が終わるともう12月です。こうして一年があっという間に過ぎてしまいます。
今年度のビュクリュカレ遺跡発掘調査は4月25日から6月25日までの2ヶ月間行なわれました。文化省からは査察官としてカマン・カレホユック博物館より考古学者のアースム・ギュルテキン氏が派遣され一緒に調査を行いましたが、彼とはすでに旧知の仲ということもありスムースに調査を進めることが出来ました。その反面、天候には恵まれず、今年も雨にたたられ作業を中止せざるをえなくなった日が何日もありました (Fig. 1)。
今年度の調査では新しいプロジェクトを始動させました。それが千葉工業大学との共同発掘プロジェクトです。千葉工業大学惑星探査研究センター、松井孝典所長と共同でヒッタイトの鉄を探るプロジェクトです。
このプロジェクトの事前準備として昨年度既に鉄滓のサンプルを日本に持ち帰って分析して頂いていました。分析は松井先生の統括のもと、岡山大学惑星物質研究所,中村栄三所長に加わっていただき行われました。
この鉄滓は2009年の調査時に、遺跡の南端にある岩陰部の地表面に大量に散布しているのを確認していました。それを分析しようという大村所長の発案のもと、松井先生に依頼しました。我々としては、これがヒッタイト時代の鉄生産と関連していたら大きな成果につながる、という気持ちがある一方で、後世のものの可能性もかなり高いのでは、という半信半疑なものでした。残念ながらそこでは年代を決める決め手となるものが見つかっていませんでした。 2015年度の分析結果については、翌年2月に東京で開催された遺跡発掘報告、研究会で既に発表されていますが、非常に興味深い結果が出ました。それは鉄滓の中に石灰が混入されている、というものです。このような技術が一体いつ頃使われたのか、というのが次の疑問です。
少し調べたところ石灰の混入に関しては、高炉では燃料と鉱石とフラックス(石灰) を溶鉱炉の上部から入れ、フラックスはスラッグ (鉄滓) を分離させやすくするために入れるのに対し、古い技術である塊鉄炉では自己フラックス効果 (self-flux) があるためスラッグ (鉄滓) を生じさせるための 追加の石灰岩が不必要であるという記述が見つかりました。
つまり、これまで知られている最も古い製鉄技術である塊鉄炉に見られる自己フラックス効果 (self-flux) が土中の石灰が同じ効果をもたらすのか、あるいは別の物質が作用しているのかがはっきりしていませんが、少なくとも石灰が入ったスラッグは高炉を用いた場合にも出てくることが理解されます。ここから、石灰を含んだスラグの存在から年代を決めることは困難であることが理解されます。
また、ヒッタイトは鉄を溶かさないで作っていたのか、という単純な疑問が頭の中にありました。というのも鉄を溶かす技術はずっと後になってから生まれたものだと聞いていたからです。
ヒッタイト時代の文書『アニッタ文書』には次のような記述があります。
73 私が戦いに出向いた時
74 プルシャンダの男は私に贈り物を持って来た
75 彼は私に鉄製の玉座と鉄製の王笏を贈り物として持って来た
76 私がネシャに戻ると
77 私はプルシャンダの男を供にした
78 彼が王座の間に入ると彼は
79 私の右側前に座る
ここに登場する鉄製の玉座と王笏は鋳鉄ではなく錬鉄から作っていたのだろうか、という疑問です。
そこでさらに調べてみると以下の記述に行き当たりました。
「(還元過程は)四〇〇度から八〇〇度あれば進行でき、温度が低ければ固体のまま還元して酸素を失った孔だらけ の海綿状の鉄になり、もっと温度が高ければ、粘いあめ状の塊になる。これを鍛錬して鉄でない部分を十分に除去す れば、立派な鉄となる。」中沢護人, 1964年『鋼の時代』岩波新書,p.24. つまり溶かさなくても鉄は作れるということのようです。だからこそ古代の鉄は低い温度でも生産できたと。また鋳鉄の製造開始は、ヨーロッパでは中世末期(14世紀頃)なのに対して、中国は紀元前4世紀頃の戦国時代(B.C.476-221年) と理解されていることがわかりました。では一体中近東、特にヒッタイトではどうだったのかという疑問が出て来ますがヒッタイトの製鉄技術はまだ詳しく解っていないようなので、ビュクリュカレ遺跡の調査で何か手がかりをつかめればと期待しています。
さてこの分析結果には松井先生が大きな興味を持たれ、ぜひこの鉄滓が採取された地点を調査しようと提案されこの調査が実現しました。その際ヒッタイト時代の鉄工房址ではないかという期待感とは裏腹に後世の工房址の可能性はないのかという不安も持ちながらこの地点の発掘を開始しました。 岩陰部での調査では、第一に鉄滓を生み出した鉄工房を見つけることを主眼としました (Fig. 2)。そこで岩陰部に1m平方のグリッドを設定し、表採を行い、地表面に分布する鉄滓の密度から工房の、特に炉址のある地点を推測しようとしました (Fig. 3)。
ところが鉄滓は岩陰部のほぼ全域に満遍なく分布しており、有意義な差異を見つけ出すことはできませんでした (Fig. 4)。そこで次にその場所の発掘を開始しました。その際、格子状に発掘を行うことで断面図作成のための断面壁を残さずに済むようにしました。その結果岩陰部中央に深い凹みのあることが明らかとなりました (Fig. 5)。しかし、岩陰部のどこにも鉄工房址を示す炉址の存在は確認できませんでした。岩陰部の堆積はどこも同じ状態で大きく分けて3つの層から構成されていました。最上層が多量の鉄滓を含む灰交じりの黒色土層。その下に岩が細かく崩れて堆積した黄色層、さらにその下に黒色土層が存在しており、その下からは岩盤が現れました (Fig. 6)。下の二つの土層は鉄滓をほとんど含んでいません。残念ながら人工物は最上層からのもので、そこからは紀元前2千年紀の土器片、イスラム時代の施釉陶器片、さらには錆びた鉄製品等がわずかに出土しました。しかし表土層であり、羊飼いがここで火を焚いた跡も存在しており、これらの遺物からこの層の年代を決定することは不可能です。これだけ大量の鉄滓と灰が存在している以上どこかで火を使っていたはずですが、炉址等の遺構も存在せず、火を用いた痕跡を見つけることができませんでした。
この結果から次に考えたことは、岩陰部の前に広がるテラス状の平坦部です。ここで鉄生産を行い、その廃棄物を岩陰部に持っていって捨てたのでは、というものです。鉄滓は岩陰部のみならずその周辺部にもわずかながら分布しています。そこでテラス部に、今回は2m平方のグリッドを設定し、ここでもまた格子状に発掘を行いました (Fig. 7, 8)。
発掘の目的は同じく鉄生産の工房址を見つけることでしたが、ここでもまた工房址を見つけることはできませんでした。
ここでは表土の下から方形の建築物の礎石が出土しました。そしてその覆土中から5枚の青銅製硬貨がまとまって出土しました (Fig. 9)。これらの硬貨の年代を決定するため、文化省のAdil Özme博士に依頼したところ、これらはアナトリア、セルジューク朝のグヤセッディン・ケイフスラヴ2世 (1236-1247年) の治世下のものとわかりました。セルジューク時代にはビュクリュカレ遺跡のすぐ下にあるチェシュニギル橋が作られています。この建物は一部屋しかなく、炉が一つ存在しているだけでした。このことからこの建物は一般住居ではなく、橋の警備のために作られた建物の可能性があります。
その下には薄い火災層が存在していました。これは斜面に薄く堆積しており、この層からは遺構は確認されませんでした。この火災層は斜面の上から崩れ落ちて堆積したように見えます。注目すべきはこの層から出土した遺物です。一つは青銅製槍先です (Fig. 10)。17.2 cmの長さを持ち、頸部が直角に曲がっており、柄に取り付けた時に外れないようになっています。また葉の部分には二つの穴が開けられています。このようなタイプは全青銅器時代から見られるもので、特にキュルテペで出土した『アニッタの槍先』と呼ばれているものに類似しています。このキュルテペ出土の槍先にはアッカド語で碑文が彫られており、『アニッタの宮殿』と記されています。この碑文からキュルテペがカーニシュであると同定されました。先ほど述べたアニッタ文書の中でアニッタがカーニシュの王になったことが書かれているからです。この槍先と同じタイプのものが出土したということは、この火災層がアッシリア商業植民地時代後半に属する可能性が高いことを示しています。その時期にビュクリュカレ遺跡にあった都市は大火災にあったものと考えられます。しかもここは都市の最南端に位置しており、都市全体が火災で焼失したことを示しています。また同じ火災層からは前2千年紀に特徴的な青銅製槍先も出土しています (Fig. 11)。わずかに発掘しただけで、戦いを示す槍先と矢尻が出土したことは、この火災が戦争によるものである可能性が高いことを示しています。この結果からビュクリュカレ遺跡はアッシリア植民地時代後期に大火災に遭い、都市全域が焼けてしまったことが理解されます。この大火災は岩山頂上部で発掘された巨石建築遺構の後期に見られる大火災と時期が一致しています。
このように、岩壁部の発掘調査では、当初の目的の鉄製作工房址を見つけることはできませんでしたが、ビュクリュカレ遺跡の歴史に関して新たな情報を得ることができました。
今年度最大の調査目的は昨年度の継続としてヒッタイト帝国時代の層を調査し、ビュクリュカレ遺跡のヒッタイトの歴史を解明することでした。そこで昨年度確認したヒッタイト時代の建築層の関係を明らかにするために、残っている礎石壁間の堆積土を発掘しました。昨年度の発掘結果からはヒッタイト帝国期に属する5つの建築層が存在する可能性が高いことを把握しましたが、これらを検証する必要性がありました (Fig. 12)。この作業によって何が問題となるかというと、ヒッタイト帝国時代、さらには前2千年紀に幾つの火災層が存在しているのか、ということです。これを把握することによりビュクリュカレ遺跡が当時置かれていた状況を推測することができるからです。火災層が多いということは、それだけ抗争に巻き込まれていたことを示しています。 ヒッタイト時代層の中で最も新しいと考えられる建築遺構であるR114を外しました。この建築遺構に属する生活面上からヒッタイト帝国時代前14世紀から12世紀に特徴的な祭儀用ミニチュア土器が2点出土しています。これが年代付けの根拠となっています。
ヒッタイト時代第2建築層は火災層を伴うもので、以前にこの火災層からヒッタイト語楔形文字粘土板文書片が出土しています。この粘土板の年代は、ロンドン大学マーク・ウィーデン博士によって15世紀後半から14世紀初頭に年代づけられていることから、それと同時期かそれよりも新しいはずです。 今年度はN5W3発掘区においてこの火災層で確認された壁W300の外の部分を発掘しました。その結果焼けた2枚の外面を確認できました (Fig. 13)。昨年度の調査で建物の内部においては2期にわたってこの建物が使われており、二度火災にあっていることが確認されていましたが、今回はそれを建物の外部においても確認し、裏付けることができました。外の面は北北東に向かって下っており、ここが当時の頂上部の端であったことが理解されます。このことはこの時期頂上部には城壁が存在しなかったことを示しており、だからこそ建物の端からすぐに斜面になっていると推測できます。
この建物の外床面上の堆積土からは多くの青銅滓が出土しており、この建物では青銅製品の製作が行われた工房が存在した可能性があります。前2千年紀の宮殿においてはこうした金属製品の政策を独占していたという報告もあり、ここビュクリュカレ遺跡においてもそれを示しているのではないでしょうか。 また象形文字が刻まれた印影の破片が一片出土していますが、小片であり象形文字の意味が理解できず、そこから明確な年代を出すことは困難です (Fig. 14)。さらに光沢を持つほどに磨研が施されたクリーム色土器で製作された動物型リュトンの頭部耳と角の部分と思われる破片が出土しています (Fig. 15)。このようなクリーム土器はヒッタイト帝国時代に特徴的な土器であり、この火災層の年代付を裏付けるものです。
第3建築層は第2建築遺構の下から見つかった遺構で、最も保存状態の良いものと言えます。斜面を利用して階段状に建物が作られており、その低い部分が良好に保存されています (Fig. 16 黄色で示した建物)。2015度発掘した部屋R130では高さ2mを超える日干し煉瓦の壁が確認されており、今年は隣の部屋R133を発掘しました。同じように高く残った壁が確認され床面に達しましたが、部屋の中は空でした。覆土中からはこの時期のものと思われる印影が一点出土しましたが、その図像はあまりはっきりしていません。
この建築遺構は北西方向に伸びており、現状では少なくとも20m以上の長さを持つことを確認しています。もうひとつ重要なことはこの建物は第2建築よりさらに北東に張り出した形で作られていることです。つまり第2建築よりも大きな建物であると言えます。この建物がどこまで伸びているのかを明らかにするために、後期鉄器時代の城壁を外す作業を開始しています。来年度もこれを継続し、これまで確認されている中で最も保存状態の良い第3建築遺構の調査を行いたいと考えています。
第4建築層に属する壁W379(黄緑色)は第3建築層の壁W113(黄土色)によって破壊されています (Fig. 17)。2015年度確認されたこの壁は北側にのみ面を持つ一列壁であることから壁の南側は土で覆われていたはずです。つまり段差のある部分にこの壁を作ったと考えられます。壁の北側の覆土は焼土層であるため、この建物が火災にあっていることが理解されます。この火災層の中からは多くの炭化した木材が出土しました。炭化材の中には角材にほぞを作って組んでいたものがあり、当時の建築技術を理解する上で貴重な資料となりました (Fig. 18)。
さらに掘り進んで床面に到達しましたが、そこには傾斜した床面が存在し、その北側には縁石と同等の機能を持っていたと思われる低い壁W405が壁W379に並行して出土しました。この空間に部屋W155という番号を付けましたが、これは通路の可能性が高いと思います(Fig. 17参照)。元々は頂上部から西側のテラス部に繋がる登り口であったものが、第3建築層によって壊されてしまったものと考えられます。W379の西端に突出した壁W392が確認されましたが、ここには入り口の扉があったと考えられます。もしかすると焼土層の中から出土した木材片はこの扉に使われていたものかもしれません。当時ここには入り口に通じる通路があったものの、第3建築によって壊されていることから、その東側の先の第3建築によって壊されていない部分にこの続きが出土する可能性があります。
さらにここに登り口が存在するとなると、それに伴う建物はこの登り口の南側に存在したはずです。これは建物の構造から見るとアッシリア商業植民地時代に建設された巨石建築物の北西壁と並行しており、その伝統を継承しているように見えます。R155の発掘で出土した一点の印影は水差しから液体を注ぐ人物の前にライオンと双頭の鷲が描かれており、それらを組紐文様が丸く取り囲んでいます (Fig. 19)。この組紐文様はアッシリア商業植民地時代の後半から古ヒッタイト時代にかけて好んで用いられた文様であることから、この印影の年代が導き出されます。印影の年代が必ずしもこの遺構の年代を示すものではない可能性もありますが、古ヒッタイト時代のものであれば建物の推定年代と一致します。
壁W379の後ろ、つまり南側には別の壁W359が存在しており、W379によって破壊されています (Fig. 20)。これが第5建築層です。ただしこの壁もW379と同様に北側にのみ面を持った壁で、同じ建築伝統に基づいて作られた建築物のようですが、ここは火災を受けていません。この壁にはこれに直交する壁W360が後付けされています。この壁はW359の壁の底部までは続いていないことからも後付けであることは明らかです。
壁W359の南側にそれに直交する形で壁W325が存在します(Fig. 20参照)。この壁も一列壁で東側にのみ面を持ちます。それゆえ壁の西側の土を止めるために築かれたものと考えています。この壁はW329に接続しています。そしてW325に直交する形で、W329, W384の前にW382が作られています。つまりW382はW325に接続させて作られており、同時期か、それより新しいものであるはずです。W329とW384は巨石建築物の2時期の壁であり、W325はそれと同時期である可能性もあります。しかしこの壁の西側の堆積土はW324から続く灰の層が存在しており、それを切る形でこの壁が作られていることがわかります。それゆえW325は二つの巨石建築の時期よりも新しいと言えます。そうなるとW384の前に作られたW382と同時期と考えるのが妥当です。これに対応する北壁はW359であるか、あるいはW359によって破壊されてしまった可能性があります。W359はその上半部では両面を持つのに対し下部では北西側にのみ面を持っています。同様にW382もその後ろのW384と同じ深さにまで続いておらず、これらの事実を考慮するとR150はW382, W325とW359から構成され、W359を作った後にW325を作り、その西側を埋め、さらにW359とW384との間を一定の高さまで埋め、その後にW382を付け加え部屋R150を作ったものと考えられます。W359の上半部の両面を持つ部分も埋め立ての後に付け加えられた可能性が高いでしょう。この空間R150がどのように使われたのかについては現段階では明らかではありません。今後R150の北東部の調査を行うことによってなんらかの糸口がつかめるかもしれません。
第6建築層は巨石建築の第2期目の建築層で、大火災に遭っています。
巨石建築の第1期が第8建築層です。この時期に巨石を用いて礎石が作られています。第2期の建築層では、確認できる限りにおいて巨石はあまり使われていません。その意味で巨石建築と言えるのは実は第1期のみとなります。しかし第2期においては第1期の礎石を利用して作られており、同じ建築伝統を踏襲していると言えます。
未だに解明できていないのが、第3建築層に属するW113によって破壊されているW379の南東側に存在し、その上にW359が作られている火災層です。これが一体どの建築層に属しているのかは現段階では不明ですが、この状況から推測すると、巨石建築の第1期よりも古いアッシリア植民地時代以前の、つまり前期青銅器時代の層に属する火災層である可能性が高いと言えます。アッシリア商業植民地時代以前にここビュクリュカレ遺跡には既に大規模な建築物が存在していた可能性があります。それは巨石建築遺構に属するテラス壁の内側覆土で埋められたさらに大きな石を用いて作られた城壁が存在していることがこれまでの発掘で確認されているからです。これは火災にあっておらず、同じ層ではなさそうですが、前期青銅器時代末期にすでに巨石建築が存在したことを示しています。前期青銅器末期というと、メソポタミアではアッカド王朝が隆盛を極め、サルゴン王とその孫のナラム・シン王がアナトリアまで遠征してきたという伝説がボアズキョイ出土のヒッタイト文書、さらにはキュルテペ出土の文書から知られています。この時代に相当する宮殿が大村正子隊長が指揮するヤッスホユック遺跡で発掘されています。またキュルテペにおいても現在盛んにこの時代の宮殿址が現在調査中です。アナトリアにおいて未だ文字資料が見つかっていないこの時代の調査研究が進められており、ビュクリュカレ遺跡の発掘調査もこの時代の解明に少しでも貢献できるのではないかと、これからの調査に期待を膨らませています。
以上のようにアッシリア商業植民地時代の巨石建築の後、ヒッタイト時代に年代づけられる5つの建築層が確認されました。このうち二つが火災にあっています。このような抗争を示す火災層を持ったビュクリュカレ遺跡の古代名が一体なんであったのかを今後の調査で解明していこうと考えています。
第8次ビュクリュカレ遺跡発掘調査(2016年)中間報告
今年度の調査もすでに折り返し地点を過ぎました。
昨年見つかったヒッタイト時代の建築遺構の関係や年代を解明することが今年度の最大の目的です。遺構の間に堆積した土を発掘調査して遺構間の切り合い関係を理解し、年代決定に寄与する遺物を探しています。
粘土板が出土している焼土層の調査では昨年度までに発掘した建築遺構が西に延び15m以上もの規模を持つ建物であることが明らかとなりました。この建物はさらに西に延びており、来年度も調査をする予定です。この焼土層からはヒッタイト語粘土板文書片が出土しているので期待を持って調査に臨んだのですが、建物の外側に堆積した焼土層からは残念ながら驚くような発見はありませんでした。(写真1)

写真1
この焼土層の下にはさらに大きな建物が存在していますが、それは後期鉄器時代の城壁(石壁)の下に伸びています。そのためヒッタイト時代の遺構を調査するためにはまずこの石壁を取り除かなくてはなりません。幅が2m、高さが2m以上の石壁を取り外すのは容易ではありません。さらにこの壁の外側は土を盛ってあり、この土を発掘、除去するのが大変な作業です。(写真2)今年の調査では1グリッド、10mの壁を外すのがやっとといったところです。ただし一昨年、この壁の取り外し作業中に「匿名タバルナ印章」と呼ばれるヒッタイト王の印影が出土しているので、ひょっとすると今年の作業中にも思わぬ遺物が出土するのではないかとわずかな期待を持ちながら作業をしています。

写真2

写真3
さらに今年度の発掘では、発掘期間とイスラム教の断食が重なり、作業員の中にも断食を行っている人が半分近くいます。これもイスラム教圏での発掘の特徴と言えます。最初にトルコで発掘に参加した1980年代、ちょうどこの時期に断食が行われていました。1年に10日ずつずれていくため30年ほど経って一回りし、再びこの時期に断食が行われています。力仕事をしている作業員には大変ですが、なんとか頑張ってもらって良い成果を出したいと思います。

写真4

写真5
それともう一つ大きなプロジェクトが動き始めました。それは千葉工業大学との共同で行うビュクリュカレ遺跡鉄製作址の調査です。これまでに遺跡南部の岩陰で多量の鉄滓が表採されており、昨年度千葉工業大学惑星探査研究センターの松井孝典先生に分析を依頼した結果、それが確かに鉃滓であることが明らかとなりました。そこで今年はその鉄滓が製作された遺構を発掘調査し、その技術、年代を明らかにすることになりました。(写真3)現在発掘区を設定し、発掘に取り掛かりましたが、最初の表面採取ですでに地表面から大量の鉄滓が採取されており期待を持って調査を行っています。(写真4、5)(6月18日)
ビュクリュカレ遺跡にて地中探査を実施しました

地中探査作業

地中探査作業
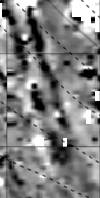
探査結果
4月30日から5月7日まで熊谷和博氏(産業技術総合研究所)により地中探査が行われました。彼は電子顕微鏡の研究開発が専門ですが、大学時代からずっとアナトリア考古学研究所の調査に参加してくれており、今年も五月の連休を使って駆けつけてくれました。
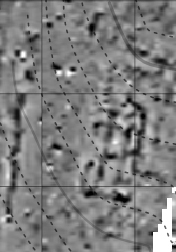
探査結果
ビュクリュカレ遺跡の土は磁気探査に向いており、これまでに大きな成果が出ています。その一つがヒッタイト特有の都市壁と門の発見です。この発見によりヒッタイトの都市の存在を確認することが出来ました。今年の磁気探査は遺跡の南西部分で行われ、約30mの規模を持つ建物が確認されました。また岩山を取り巻く形で伸びる道のような構造も見つかりました。予備調査を含めて9年間の調査で遺跡のかなりの部分の探査が終わりました。今後は遺構が見つかった部分をより詳細に探査していく予定です。(5月11日)
第8次ビュクリュカレ遺跡発掘調査(2016年)を開始しました

テント設営作業
2016年4月25日より第8次ビュクリュカレ遺跡発掘調査を開始しました。本年度は研究所の隣にあるカマン・カレホユック考古学博物館からアースム・ギュルテキンさんが査察官として派遣され、2ヶ月間一緒に調査を行います。

保護屋根取り外し作業

保護屋根取り外し作業

清掃作業
初日にはテントの設営と屋根外しを予定していましたが、午後になって強風が出てきたため、屋根外しは翌日に延期となりました。二日目は屋根外しを始めたものの10時頃から雨が降り始め、再び作業を中止せざるをえませんでした。明日以降の天気は問題なさそうです。

初日の発掘調査参加者
これらの作業を行う一方で、発掘開始の挨拶に関係機関を回りました。県知事、移民局、県文化局、ジャンダルマ(郡警察)、郡長などですが、8年目にもなると顔なじみの方が増え、手続きもスムーズに進みます。発掘調査を継続していく上で最も重要なことの一つは、こういった「良い人間関係を築く」ことだということはカマン・カレホユック遺跡の調査から学んだことです。
本年度の発掘調査は、ヒッタイト帝国時代層を重点的に調査する予定で、これまで以上の成果を期待して作業に取りかかっています。(4月28日)
![Fig. 1[クリックで拡大]](../images/excavation/bk_2016_4_1_t.jpg)
![Fig. 2[クリックで拡大]](../images/excavation/bk_2016_4_2_t.jpg)
![Fig. 3[クリックで拡大]](../images/excavation/bk_2016_4_3_t.jpg)
![Fig. 4[クリックで拡大]](../images/excavation/bk_2016_4_4_t.jpg)
![Fig. 5[クリックで拡大]](../images/excavation/bk_2016_4_5_t.jpg)
![Fig. 6[クリックで拡大]](../images/excavation/bk_2016_4_6_t.jpg)
![Fig. 7[クリックで拡大]](../images/excavation/bk_2016_4_7_t.jpg)
![Fig. 8[クリックで拡大]](../images/excavation/bk_2016_4_8_t.jpg)
![Fig. 9[クリックで拡大]](../images/excavation/bk_2016_4_9_t.jpg)
![Fig. 10[クリックで拡大]](../images/excavation/bk_2016_4_10_t.jpg)
![Fig. 11[クリックで拡大]](../images/excavation/bk_2016_4_11_t.jpg)
![Fig. 12[クリックで拡大]](../images/excavation/bk_2016_4_12_t.jpg)
![Fig. 13[クリックで拡大]](../images/excavation/bk_2016_4_13_t.jpg)
![Fig. 14[クリックで拡大]](../images/excavation/bk_2016_4_14_t.jpg)
![Fig. 15[クリックで拡大]](../images/excavation/bk_2016_4_15_t.jpg)
![Fig. 16[クリックで拡大]](../images/excavation/bk_2016_4_16_t.jpg)
![Fig. 17[クリックで拡大]](../images/excavation/bk_2016_4_17_t.jpg)
![Fig. 18[クリックで拡大]](../images/excavation/bk_2016_4_18_t.jpg)
![Fig. 19[クリックで拡大]](../images/excavation/bk_2016_4_19_t.jpg)
![Fig. 20[クリックで拡大]](../images/excavation/bk_2016_4_20_t.jpg)